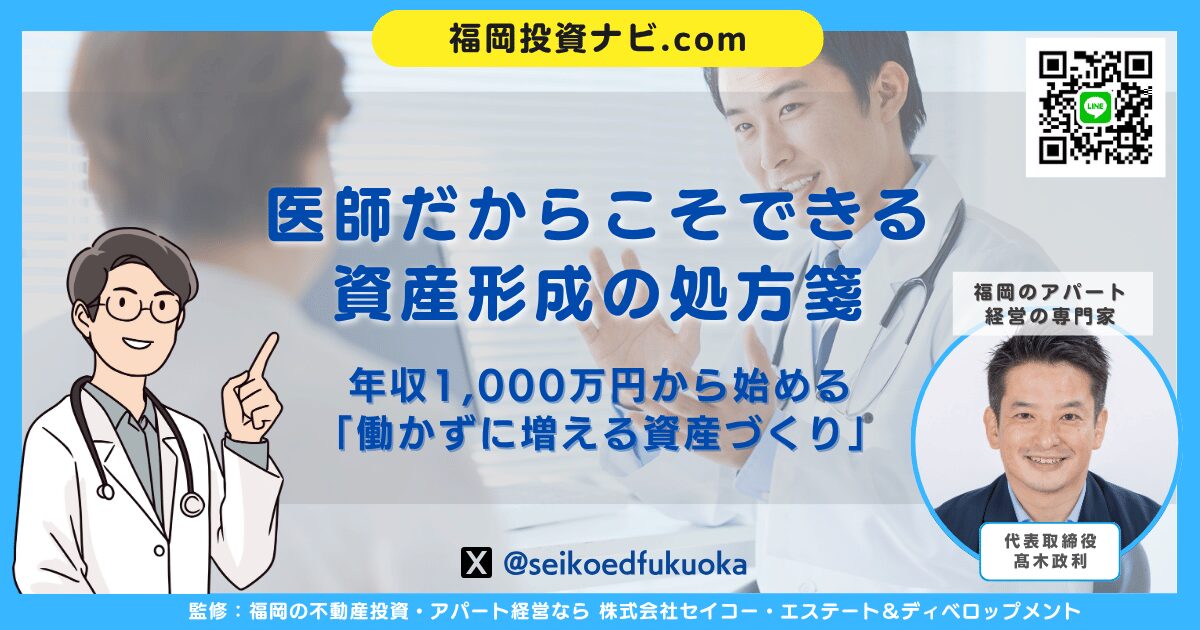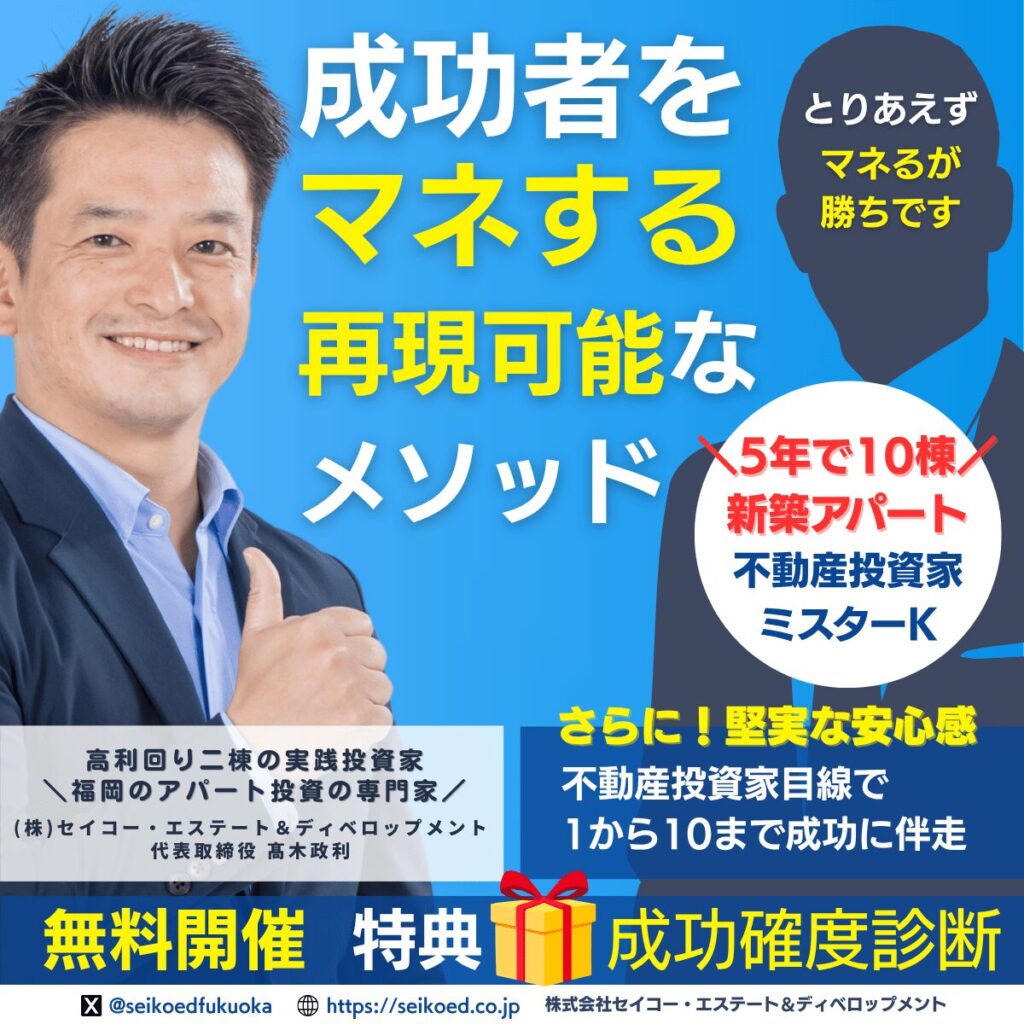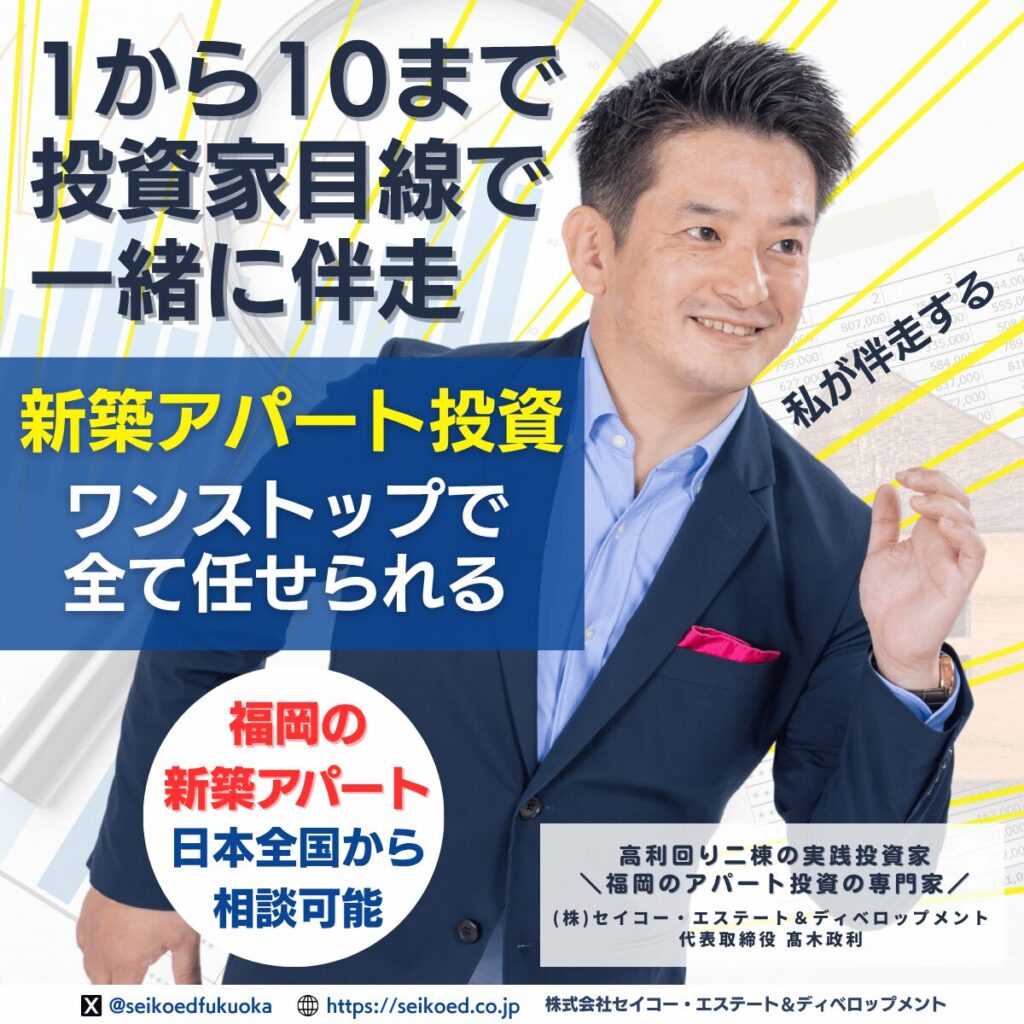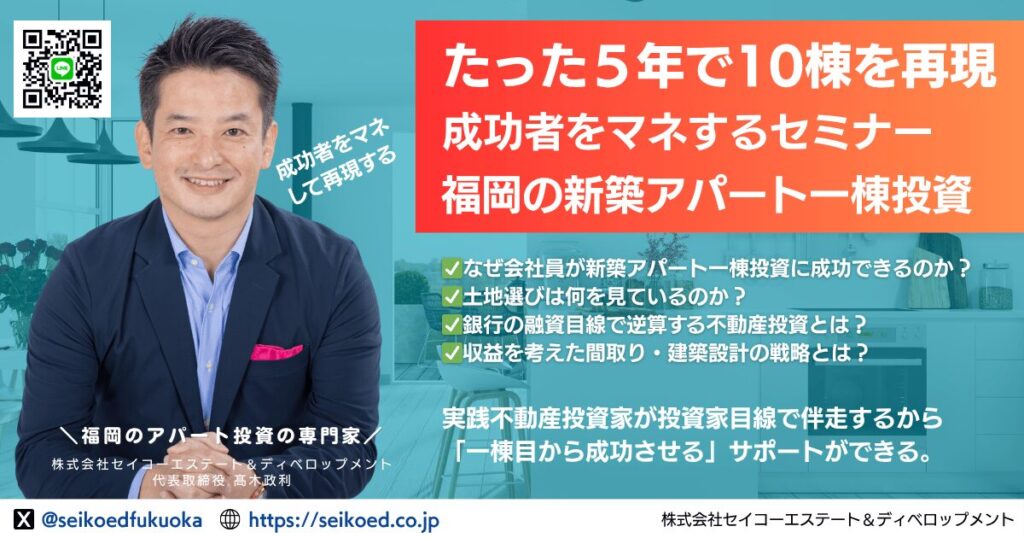医師という職業は、高い信用力と安定収入を武器に、不動産投資の世界でも圧倒的に有利な立場にあります。
しかしその一方で、「営業トークに乗って区分マンションを買って失敗した」「融資は通るけれど二棟目が続かない」といった相談も少なくありません。
本記事では、医師が不動産投資を始める際に絶対に押さえるべき基礎知識と成功ステップを徹底解説します。
節税・融資・物件選び・リスク管理まで、勤務医・開業医それぞれの立場に合わせた“正しい始め方”を紹介。
さらに、セイコー・エステート&ディベロップメントが実際に支援してきた
「一棟目から二棟目・三棟目へと融資が続く成功事例」も交えて、医師が安心して資産形成を進める方法をお伝えします。

高木 政利(たかぎ まさとし)
株式会社セイコーエステート&ディベロップメント 代表取締役
福岡の不動産投資・アパート経営の専門家
福岡市を拠点に、不動産投資の企画・建築・資産形成支援を手がける「株式会社セイコーエステート&ディベロップメント」代表。一棟アパートの新築・土地活用・空室対策・創業融資支援に精通し、福岡エリアの実需と投資ニーズを熟知したプロフェッショナル。これまでに数十件以上の投資用不動産の設計・建築・収益改善を手がけ、多くの個人投資家や経営者から信頼を得ている。
「福岡で堅実な不動産投資をしたい方に、現場視点でリアルな情報を届けたい」という想いから、『福岡投資ナビ』を運営。
なぜ“医師”だからこそ不動産投資を始めるべきか
医師は一般の会社員や経営者とは異なる「高い信用力」と「安定した収入」を持つ一方で、時間の制約が大きい職業です。実はこの特性こそが、不動産投資と非常に相性が良い理由です。ここでは、医師がなぜ不動産投資に向いているのか、その根拠と注意点を詳しく解説します。
医師の属性が不動産投資に向く理由(高所得・与信・時間の制約)
節税メリット:給与所得×減価償却・損益通算の仕組み
医師は高い給与所得を得ている分、所得税・住民税などの税負担が非常に大きいのが現実です。
不動産投資では、建物の減価償却費やローン利息、修繕費などを経費として計上することで、課税所得を圧縮できます。
たとえば、年間家賃収入1,000万円・経費400万円の場合、実質的な課税所得を600万円まで下げられ、所得税率40%の医師であれば年間約160万円の節税効果も見込めます。
さらに、損益通算により不動産の赤字分を給与所得と相殺できるケースもあり、手取りを増やしながら資産形成を進めることが可能です。
融資環境の優位性:医師ならではの与信力
医師は、金融機関から「超優良属性」として扱われます。
これは、社会的信用の高さと安定収入が理由で、銀行側にとっても「返済リスクが低い顧客」と見なされるためです。
特に、勤務医であっても年収1,000万円を超えるケースが多く、不動産投資ローンの審査通過率は一般の会社員より圧倒的に高い水準です。
ただし、銀行によっては「医師専門融資枠」などを設けており、表面金利や返済期間の交渉によって将来の資産拡大に差が出る点には注意が必要です。
忙しい本業でもできる:管理委託で“手をかけずに資産へ”
不動産投資は「働く時間を切り売りしない資産運用」です。
医師のように勤務時間が不規則でも、管理会社に委託すれば運営のほとんどを自動化できます。
入居者募集・家賃集金・修繕対応をすべて任せることで、医師は本業に集中しながら安定収益を積み上げることが可能です。
また、医師の退職金・開業準備資金の運用先としても優秀であり、早期に始めるほど「複利効果」で大きなリターンを得られるでしょう。
医師だからこその留意点・“油断できない”側面
過大な借入リスク・空室リスク・物件選定ミス
医師は融資が通りやすい反面、営業マンの勧誘で過剰な借入をしてしまうリスクもあります。
とくに、都心区分マンションなどは「節税になる」と説明されるケースが多いものの、実際にはキャッシュフローがマイナスになる事例も少なくありません。
医師にとって大切なのは、本業収入に頼らずとも収益が安定する“プラス収支の物件”を選ぶこと。
立地・利回り・修繕コストの3点を総合的に判断することが、リスク回避の第一歩です。
将来の開業/医院経営への影響 – 負債過多の危険
開業医を目指す方にとって、不動産投資ローンが開業資金の調達に影響する可能性があります。
金融機関は、個人の総借入額を「信用枠」として管理しており、不動産投資ローンを組みすぎると開業資金の融資枠が減少することも。
そのため、勤務医時代に無理のない規模で不動産投資を始めることが重要です。
融資の順序やタイミングを誤らなければ、不動産収入と医院経営を両立することも十分に可能です。

アパート経営の専門家
髙木政利
「医師の方は融資面で非常に有利な立場にありますが、その分だけ“借りすぎて失敗する”ケースも多く見てきました。
私たちは一棟目から二棟目・三棟目へとつながる融資戦略を重視し、収益を確実に積み上げていくロードマップを設計しています。
その方法を詳しく知りたい方は、下記の無料セミナーで具体的な戦略をお伝えしています。」
医師向け不動産投資の“始め方”ステップ
不動産投資は、正しいステップを踏むことでリスクを抑えながら安定的な収益を得られます。ここでは、医師が最初の一棟を成功させ、その後の拡大にもつながる“正しい始め方”を解説します。
目的とシナリオを明確にする(節税・副収入・将来開業準備)
医師ライフステージ別の目標設定(勤務医/転科/開業医)
医師のキャリアは、勤務医・転科・開業医などライフステージによって大きく異なります。
それぞれに最適な不動産投資の目的があります。
- 勤務医の場合: 安定収入を活かし、節税+副収入の基盤づくり
- 転科・独立前: 開業資金の自己資本を強化する資産運用
- 開業医の場合: 医療法人の経営安定化・退職金代替・相続対策
目的を明確にすることで、「今の投資」と「将来の展開」が一本の線でつながり、迷いのない判断ができるようになります。
自己資金・キャッシュフロー・借入可能額の整理
自己資金の目安と年収目安(医師の場合)
医師が不動産投資を始める際の目安は、自己資金500万円〜1,000万円程度が一般的です。
年収1,000万円前後であれば、5,000万円〜1億円規模のアパート投資も可能です。
大切なのは、頭金をすべて投入するのではなく、運営中の予備資金(半年分程度)を残すこと。
突然の修繕や入居者退去が発生しても、キャッシュフローを維持できる資金設計を行いましょう。
借入条件と返済余力のチェックリスト
- 月収の25〜30%以内で返済を抑える
- 返済比率はDSCR(債務返済余裕倍率)=1.2以上を確保
- 金利上昇リスクを想定し、2%上昇時でも収益が黒字か確認
- 複数棟保有を見据え、1棟目から「銀行評価が伸びる設計」を意識
このような条件を満たすことで、次の融資(2棟目・3棟目)への拡大もスムーズになります。
物件タイプの選定 – 医師ならではの選び方
区分マンション vs 一棟アパート/地方 vs 都心 vs 福岡モデル
医師の不動産投資は、「時間をかけずに安定収入を得たい」ニーズが多いため、一棟アパート投資が最も相性が良い傾向にあります。
区分マンションは管理が楽ですが、利回りが低く、融資評価が伸びにくいため、拡大戦略には不向きです。
一方、福岡のような地方都市では、土地付き新築アパートで利回り6〜8%が実現可能。
都心よりも低価格で始められるため、医師が初めての投資で挑戦するには理想的なエリアといえます。
医師として「将来の開業用途」も視野に入れた物件活用例
たとえば、1階をテナントとして将来クリニック開業に転用できるアパートを選べば、資産運用と開業準備を両立できます。
また、土地付き一棟物件を保有することで、医療モール・高齢者向け住宅への転用など、将来的な出口戦略も柔軟になります。
金融機関/融資交渉のポイント
医師という属性を活かす融資戦略と落とし穴
医師は優遇される立場にあるものの、銀行は「返済比率」「エリア」「資産背景」を厳格に見ています。
重要なのは、初回融資で“銀行評価が伸びる物件”を選ぶこと。
1棟目で成功すれば、2棟目・3棟目の融資枠が自動的に広がります。
逆に、収益性が低い区分マンションなどを選ぶと、“評価が伸びない物件”として次の融資が止まるリスクもあります。
セミナーでは、こうした「融資が続く」成功パターンを実例とともに解説しています。
信頼できる不動産会社・管理会社の選び方
医師が見落としがちな「営業マンの勧誘パターン」と対応策
医師は営業マンにとって「狙われやすい」存在です。
- 「節税になります」
- 「医師限定の特別プランです」
- 「ローンはすぐ通ります」
こうした言葉に惑わされて、収益性が低い物件をつかまされるケースが後を絶ちません。
重要なのは、「売る会社」ではなく「投資家の立場で伴走してくれる会社」を選ぶこと。
セイコー・エステート&ディベロップメントのように、土地仕入れから融資・建築・運用までをワンストップで支援する会社を選ぶと、投資判断の精度が格段に上がります。
契約・引き渡し・運用開始までのロードマップ
開業医・勤務医それぞれに対応した“忙しくてもできる”運用体制
不動産投資の成功は、購入後の「管理」にかかっています。
勤務医であれば、全管理を外部委託し、月次レポートで収益を確認するスタイルが最適。
開業医であれば、法人での保有や節税スキームを組み合わせ、経営の安定化を図るのも有効です。
いずれの場合も、「投資=時間を奪うもの」ではなく、“時間を生む仕組み”として活用する視点が欠かせません。

「医師の方は、一棟目での融資設計を正しく行えば、その後の二棟目・三棟目は自然と拡大していきます。
私たちのセミナーでは、“融資が止まらない”物件の選び方と金融機関への戦略的アプローチを具体的に学べます。
短期的な節税ではなく、長期的な資産形成を本気で考える医師の方にこそ参加していただきたい内容です。」
医師が知っておくべきリスクと回避策
医師は与信が高く融資を受けやすい一方で、営業トークや拡大スピードに流されると、キャッシュフローや将来の開業資金に支障をきたします。ここでは、実務で起きやすいリスクを“原因→症状→対策”の順に整理し、二棟目・三棟目へ着実に進むための回避策を解説します。
空室・家賃下落リスクへの備え
- 需給ミスマッチ:周辺に新築供給が続く/入居者属性と間取りがズレる
- 募集力不足:家賃設定が相場から乖離/広告費・仲介協力度が弱い
- 維持管理の劣化:内装・外装・共用部の小さな劣化放置→内見離脱
- 賃料査定の二重化:ポータル実勢+管理会社ヒアリングで相場±3%に収める
- リーシングKPI:反響数/内見数/申込率を月次で可視化、遅延時は広告費を一時増額
- 商品力強化:1室10〜20万円のピンポイント改修(照明・アクセントクロス・洗濯機置き場・Wi-Fi)でCVRアップ
- 間取りの“地域適合”:福岡郊外は1LDK/2LDK需要が強いエリアが多く、供給状況を必ず確認
金利上昇・返済負担増のシナリオ
原因と症状
- 変動金利の上昇で毎月返済が増え、手残りが薄くなる
- 複数棟保有時にDSCR低下→追加融資が止まる
回避策(シナリオ設計)
- ストレステスト:金利+2.0%・空室率+5ptでもDSCR1.2以上を維持
- 返済期間×固定比率の最適化:一部を固定金利でヘッジ/期間短縮はCFと相談して段階的に
- 繰上返済のルール化:「簿価利回り>貸出金利+2%」の余剰CFは年1回の部分返済へ
法規制・税制変更・減価償却の罠
起きやすい論点
- 減価償却“だけ”を狙った買い→キャッシュフローマイナスの固定化
- 用途制限・建ぺい容積の見落とし→増改築・転用の自由度が低い
- 固定資産税・都市計画税の増額要因(評価替え・設備更新)
回避策(実務ポイント)
- PL(損益)重視:“税効果+CF黒字”の両立が原則
- 用途地域・条例の事前確認:将来の医療モール/高齢者向け住戸への転用余地をチェック
- 減価償却の“偏り”を平準化:築浅・築古のミックス保有で税効果の年次ブレを抑える
医師としての“過負債”が医院開業やキャリアに影響するケース
典型的なつまずき
- 勤務医時代に区分を多棟保有→返済比率上昇で開業資金の審査が厳格化
- 資産管理法人と個人の連帯保証が過度→自由な金融機関選択が難しくなる
回避策(順番のデザイン)
- “評価が伸びる一棟目”を最優先:土地付き新築一棟で積算・収益のバランスを確保
- 借入の“分散”:同一行集中を避け、保証・担保の設計を最初から最適化
- 開業スケジュールとの整合:5年先の開業仮シナリオを置き、総借入上限から逆算
ケーススタディ:失敗例から学ぶ(医師×不動産投資)
勤務医時代に借入過多 → 開業準備で与信不足になった例
- 背景:節税目的の区分×3。CFは微赤、与信枠を圧迫
- 症状:開業資金で希望額が下りず計画遅延
- 教訓:初手は積算が出る一棟でCF+評価を両立/区分の売却or借換で与信を回復
節税目的で物件購入 → 管理放置・修繕費膨らみ大きくなった例
- 背景:営業トークで築古利回り高を購入、運営KPI未整備
- 症状:退去時コスト増/想定賃料入らず赤字固定化
- 教訓:PM月次レポートで反響・内見・申込を管理/商品力改善に毎年予算化

アパート経営の専門家
髙木政利
「医師の方は融資が通りやすい=拡大が早い分、順番を誤ると二棟目以降が詰まりやすいのが実態です。私たちは“銀行評価が伸びる一棟目”を設計し、DSCRと積算の両輪で三棟目までのロードマップを提示します。手離れのよい運営体制まで含めて設計できると、失速を防げます。」
二棟目・三棟目につなげる融資戦略を学ぶ
医師向け/福岡・地方で始める不動産投資の強み
都心の価格高騰で表面利回りが圧縮するなか、福岡・地方は価格帯・賃貸需要・将来の転用余地のバランスがよく、医師の時間制約×拡大戦略と相性が抜群です。ここでは、地方投資の優位と実装ポイントを整理します。
なぜ地方(特に福岡)で医師が不動産投資を始めるべきか?
都心価格高騰と比較した地方の割安物件&融資条件の可能性
- 初期投資の適正化:同額予算で都心の区分→福岡の一棟へ
- CF安定性:賃料下落耐性と修繕・税負担の相対軽さで手残りが厚い
- 評価両立:積算(底地価)+収益のバランスが取りやすく、追加融資へつながりやすい
医療インフラ・地域医師体制・開業機会との連動性
- 人口集積×医療需要:病院・大学・製造拠点など安定雇用に支えられた賃貸需要
- 医師の将来設計と親和:クリニック併設・医療モール等の転用余地を持つ土地活用が可能
地方・福岡での物件選びのポイント(立地・市場・管理構造)
立地・市場
- 駅距離×生活動線:最寄り徒歩10分以内 or 駐車場2台以上で需要厚い
- 求人・学校・病院の分布:看護学校・大学・病院近接は単身〜DINKSまで広くカバー
- 供給過多の見極め:建築確認情報・着工統計を確認して将来の空室圧力を回避
管理構造・PM体制
- リーシングの地場力:地元仲介網×広告運用の実績がある管理会社を選定
- 原状回復の基準表:退去〜再募集を14〜21日で回す運用ルール
- 家賃保証とサブスク施策:Wi-Fi無料・宅配BOX・小型ペット可等で差別化
医師ならではの“地域連携活用”構想(クリニック併設・医療モール・サービス付き住宅)
実装アイデア
- 1階テナント×上層住居:将来自院の外来/調剤併設へ転用可能な間口と駐車動線
- 高齢者需要:看護・介護人材の雇用圧と連携しサービス付き住戸で安定稼働
- 医療モール化:内外装のスケルトン・インフィル設計でテナント入替の自由度を担保
成功モデル/医師が地方物件で資産構築している事例(仮想ケース)
ケースA(勤務医→二棟拡大)
- 購入:福岡郊外・新築一棟(1LDK×8戸)表面7.2%
- 運営:Wi-Fi無料・宅配BOX・敷礼調整で初年度満室
- 結果:DSCR1.35を維持し2年目で二棟目承認
ケースB(開業医×医療モール転用)
- 購入:駅徒歩8分・1階テナント可の一棟
- 運用:当初は住居100%→5年目に1階を自院外来へ転用
- 結果:賃料ミックスで収益安定化+クリニック集患シナジー

アパート経営の専門家
髙木政利
「福岡の新築一棟は、積算と収益のバランスが取りやすく、二棟目・三棟目の融資へ接続しやすいのが強みです。駅距離・駐車動線・テナント転用余地を最初から設計すれば、負けないポートフォリオを短期間で組めます。」
よくある質問(FAQ)
医師の方から特によくいただく質問を、現場の実例とともにまとめました。不動産投資を検討し始めた段階で知っておくべき疑問点を整理し、リスクを最小化して一棟目を成功に導くためのヒントをご紹介します。

アパート経営の専門家
髙木政利
「医師の方は、一般のサラリーマンよりも金融機関からの信頼が厚く、融資枠の拡張性があります。
しかし、一棟目の設計を誤ると二棟目が止まるという落とし穴も多い。
私たちのセミナーでは、“融資が続く物件選び”と“銀行評価を高める戦略”を実例で解説しています。」
まとめ
ここまでの内容を通じて、医師が不動産投資を成功させるためのポイントは明確です。
医師という特性を活かしながら、リスクを抑え、将来のキャリアや開業準備と両立させる資産戦略を組み立てることが重要です。
医師という属性を活かし、「資産形成・節税・将来の開業準備」を兼ねた不動産投資が可能
医師は他の職業に比べて、安定収入・社会的信用・金融機関の与信評価という3つの強みを持っています。
この強みを最大限に活かすことで、本業を続けながら“働かなくても資産が増える仕組み”を構築できます。
特に福岡エリアの一棟新築は、土地付きで積算評価が出やすく、キャッシュフローも安定するため、
将来の医院経営とのシナジーも期待できます。
ただし、物件選び・借入計画・運用管理には慎重さが不可欠
医師は「借りられる金額が大きい」ため、誤った順番で購入してしまうと、融資が止まり拡大が困難になるリスクがあります。
したがって、最初の一棟目こそ“融資評価が伸びる設計”にこだわることが成功の分岐点です。
また、運用段階では管理会社との情報共有とキャッシュフロー管理の定期確認が欠かせません。
数字に強い医師だからこそ、投資も「検査値をモニタリングする感覚」で管理するのが成功の秘訣です。
今すぐできるアクション3つ
自己資金の棚卸しを行う
頭金+予備資金+手元流動性を明確にし、“借りても無理のない範囲”を数値化しましょう。
物件市場を定点観測する
福岡市内・郊外の新築一棟アパート市場を毎月チェックし、利回りと価格相場を把握します。
信頼できる専門家・会社へ相談する
融資・建築・運営の全体を見据えたパートナーを選ぶことが重要です。
セイコー・エステート&ディベロップメントでは、「最初の一棟目から三棟目までの資産形成計画」を個別に設計しています。
さらに詳しく知りたい方へ
福岡で不動産投資を検討している医師の方は、まずは一棟目の融資戦略を学ぶセミナーから始めてみてください。
少人数制で、実際の事例や銀行交渉のリアルなノウハウを公開しています。

「医師の方は、最初の一棟目で融資戦略を誤らなければ、自然と二棟目・三棟目へと道が開けます。
私たちは、“10年で10棟・FIREを目指すための現実的ステップ”を、福岡という堅実な市場で実践的にお伝えしています。
まずはセミナーで、一棟目から成功するための具体策を手に入れてください。」
【写真で見る】福岡の新築アパート完成までのリアルなステップ
STEP1:更地の確認と購入判断 1カ月目


更地状態(福岡市南区) 地盤・周辺道路・日当たりなどを現地確認。成功する新築アパート投資の起点は、確かな土地選定から始まります。
STEP2:間取り設計・建築プラン策定


設計図と打ち合わせ風景 福岡エリアの入居者ニーズを反映したロフト付き1Kなど、エリア特性に応じたプランニングが大切です。
STEP3:基礎・上棟工事 2ヶ月目~4カ月目
基礎・構造工事中の写真 長期的な安全性と保全コストの削減につながる重要な施工工程。職人の腕が光るステージです。




STEP4:内装・設備工事 5カ月目~7カ月目


若年層の入居者に好まれる清潔感・使いやすさを追求した設備導入で、長期入居を実現します。
STEP5:完成・引き渡し 8カ月目


完成後の外観・内観写真 完成後の即入居対応が可能なよう、施工・管理部門と連携してスピーディーな仕上げを実施。

完成までの各ステップは、見えない”安心”を可視化する工程です。現地での確認・丁寧な施工・設計の工夫、それぞれが投資価値を高める鍵になります。実際の現場で培ったノウハウをご体験ください。